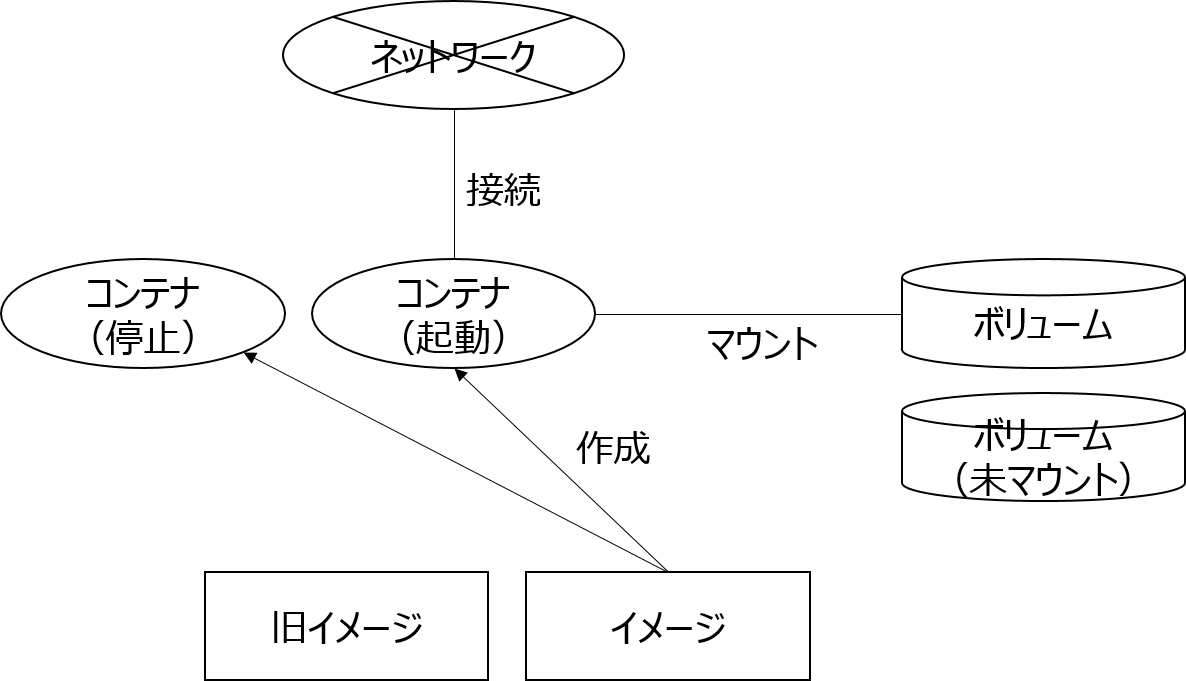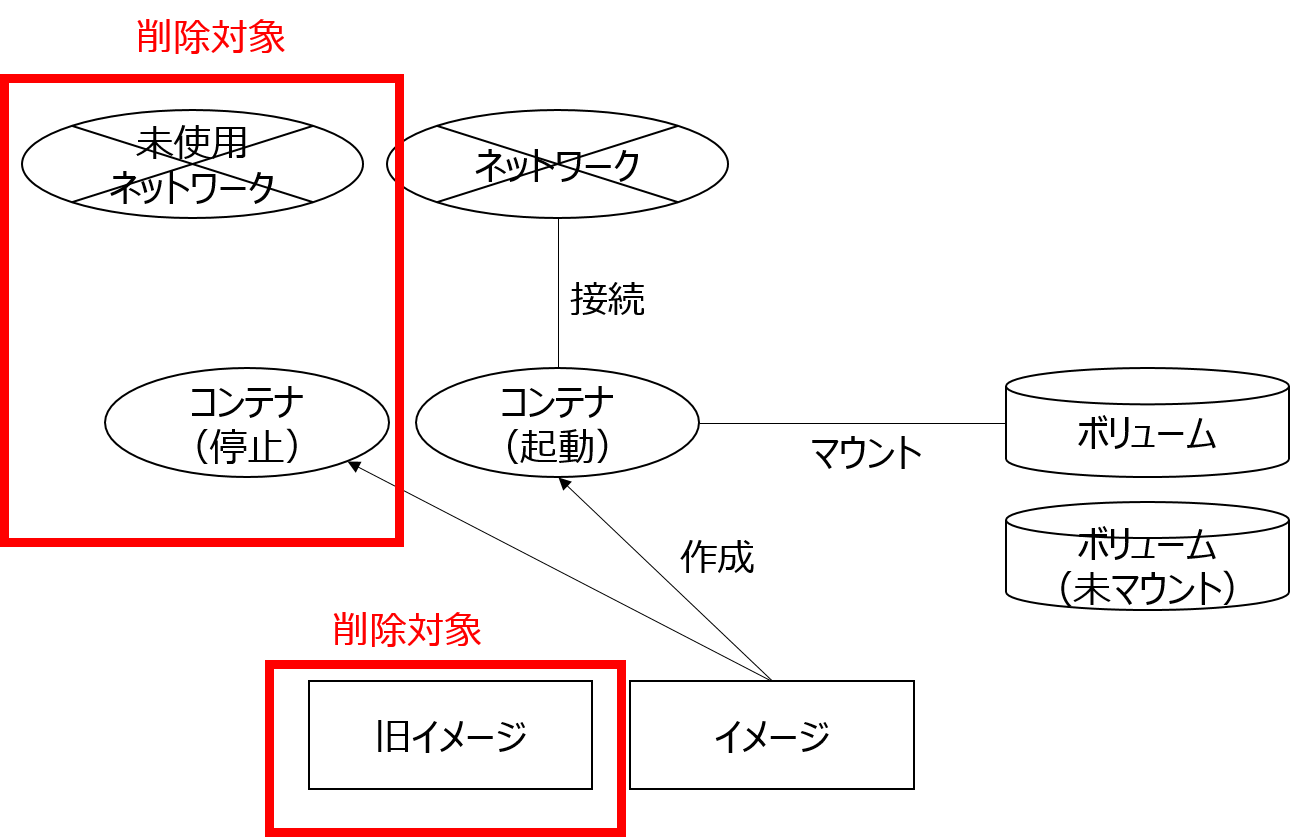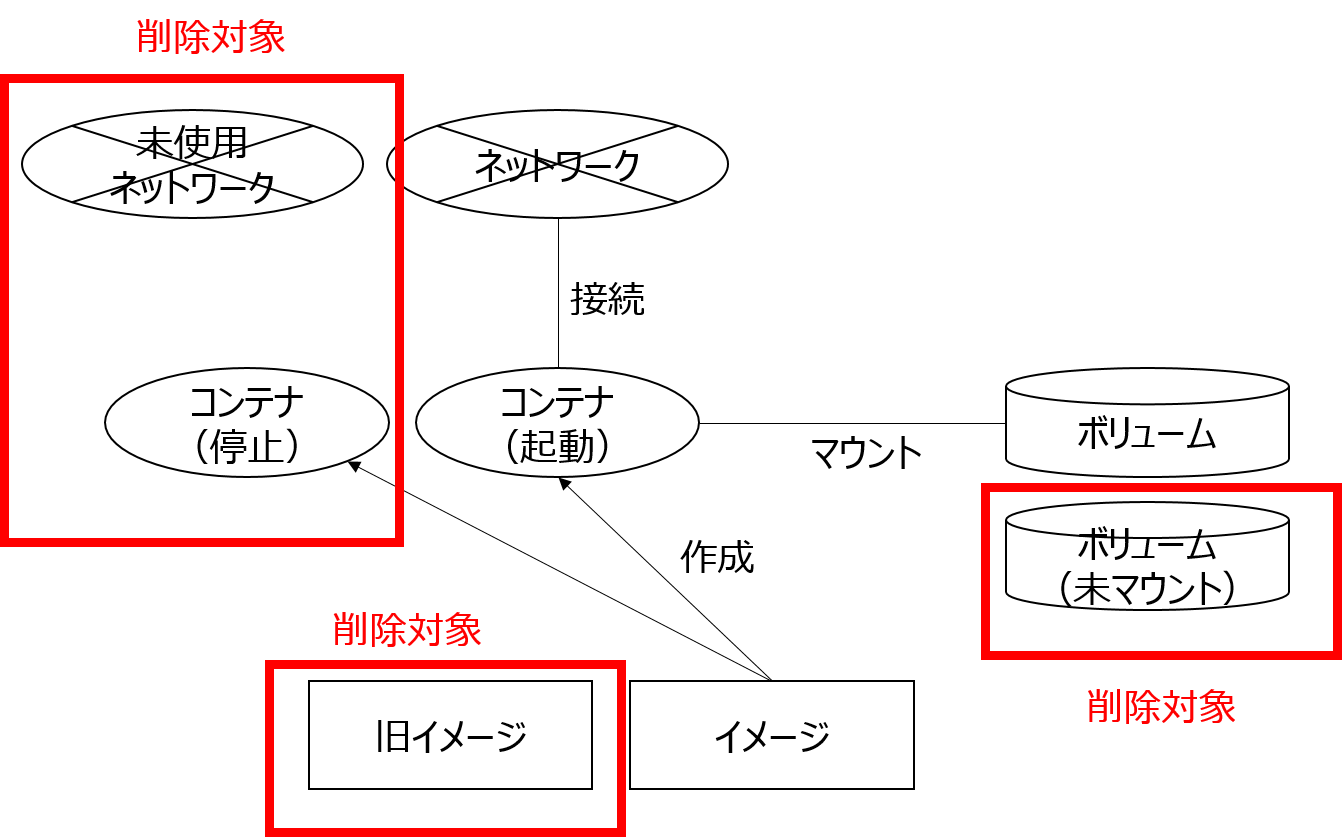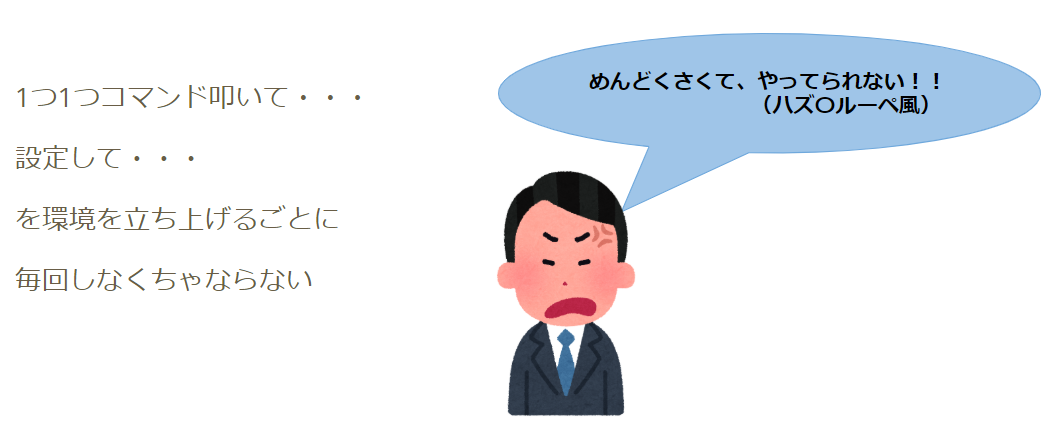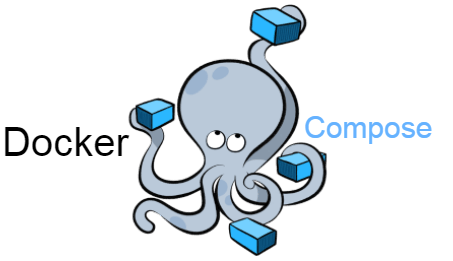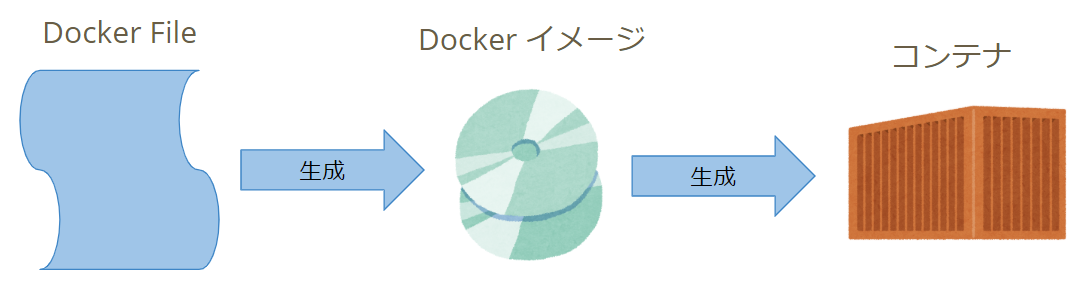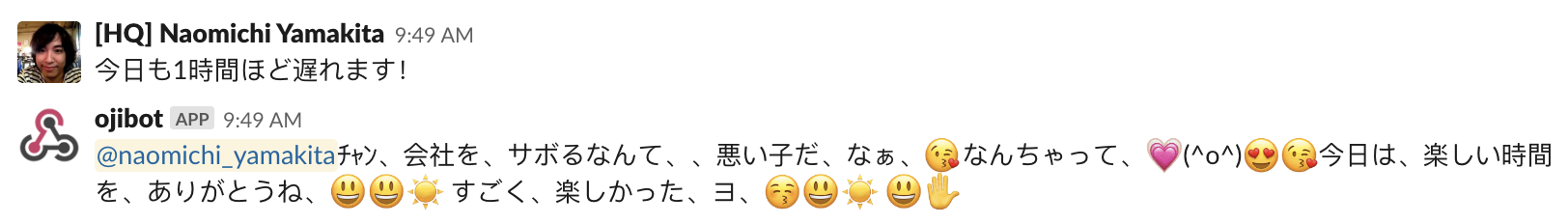- 投稿日:2019-06-07T23:37:06+09:00
一足遅れて Kubernetes を学び始める - 15. セキュリティ -
ストーリー
- 一足遅れて Kubernetes を学び始める - 01. 環境選択編 -
- 一足遅れて Kubernetes を学び始める - 02. Docker For Mac -
- 一足遅れて Kubernetes を学び始める - 03. Raspberry Pi -
- 一足遅れて Kubernetes を学び始める - 04. kubectl -
- 一足遅れて Kubernetes を学び始める - 05. workloads その1 -
- 一足遅れて Kubernetes を学び始める - 06. workloads その2 -
- 一足遅れて Kubernetes を学び始める - 07. workloads その3 -
- 一足遅れて Kubernetes を学び始める - 08. discovery&LB その1 -
- 一足遅れて Kubernetes を学び始める - 09. discovery&LB その2 -
- 一足遅れて Kubernetes を学び始める - 10. config&storage その1 -
- 一足遅れて Kubernetes を学び始める - 11. config&storage その2 -
- 一足遅れて Kubernetes を学び始める - 12. リソース制限 -
- 一足遅れて Kubernetes を学び始める - 13. ヘルスチェックとコンテナライフサイクル -
- 一足遅れて Kubernetes を学び始める - 14. スケジューリング -
- 一足遅れて Kubernetes を学び始める - 15. セキュリティ -
前回
一足遅れて Kubernetes を学び始める - 14. スケジューリング -では、AffinityなどでPodのスケジューリングについて学習しました。今回は、セキュリティについて学習します。
サービスアカウント
Podで実行するためのプロセスを制御するために割り振られるアカウントのことをサービスアカウントというそうです。
sample-serviceaccount.yamlapiVersion: v1 kind: ServiceAccount metadata: name: sample-serviceaccount namespace: default imagePullSecrets: - name: hogehogeこれをapplyしてみます。
pi@raspi001:~/tmp $ k apply -f sample-serviceaccount.yaml pi@raspi001:~/tmp $ k get serviceaccounts sample-serviceaccount -o yaml ... secrets: - name: sample-serviceaccount-token-4xhgmサービスアカウントが作成されました。また、imagePullSecretsの内容がsecretsに登録されました。(sample-serviceaccount-token-4xhgm)
imagePullSecretsはprivateなdockerレジストリに使います。pi@raspi001:~/tmp $ k get secrets sample-serviceaccount-token-4xhgm -o yaml apiVersion: v1 data: ca.crt: ... namespace: ZGVmYXVsdA== token: ... kind: Secret metadata: annotations: kubernetes.io/service-account.name: sample-serviceaccount kubernetes.io/service-account.uid: 4bd076da-8854-11e9-af26-b827eb8ccd80 creationTimestamp: "2019-06-06T12:12:04Z" name: sample-serviceaccount-token-4xhgm namespace: default resourceVersion: "584634" selfLink: /api/v1/namespaces/default/secrets/sample-serviceaccount-token-4xhgm uid: 4bfbe8bb-8854-11e9-af26-b827eb8ccd80 type: kubernetes.io/service-account-token認証に必要なtokenが登録されていますね。
RBAC (Role Based Access Control)
RBACは、さきほど作成したサービスアカウントと、どういった操作を許可するのかを定めたRoleを紐付け(RoleBinding)して、権限管理をします。1つのRoleに対して複数のサービスアカウントをRoleBindingできます。
RBACは、2つのレベルがあり、1つはNamespaceレベルで、もう一つはクラスタレベルがあります。
設定範囲がクラスタの方が大きい感じです。(namespace横断して設定する場合はクラスタレベルにする)
- RoleとClusterRole
- RoleBindingとClusterRoleBinding
操作の種類ですが、どのDeploymentやDaemonSetのようなリソースに対して下記のものがあります。
* 全ての処理 create 作成 delete 削除 get 取得 list 一覧取得 update 更新 patch 一部変更 watch 変更の追従 今回はKubernetes道場 20日目 - Role / RoleBinding / ClusterRole / ClusterRoleBindingについてを参考に進めます。
新しく作ったサービスアカウントでコンテキストを作成し、そのアカウントからPod情報を取得できるか試してみます。
そのためには、サービスアカウントの認証情報を通しておく必要があります。
※ RoleとClusterRoleに大きな違いはないため、Roleを試します。pi@raspi001:~/tmp $ TOKEN=$(k get secret/sample-serviceaccount-token-jd279 -o json | jq -r .data.token) pi@raspi001:~/tmp $ DECODE_TOKEN=$(echo -n $TOKEN | base64 -d) pi@raspi001:~/tmp $ k config set-credentials sample-serviceaccount --token $DECODE_TOKENでは、コンテキスト(sample-sa-context)を作成して、それを使用します。
pi@raspi001:~/tmp $ k config set-context sample-sa-context --user sample-serviceaccount --cluster kubernetes pi@raspi001:~/tmp $ k config use-context sample-sa-context pi@raspi001:~/tmp $ k config get-contexts CURRENT NAME CLUSTER AUTHINFO NAMESPACE kubernetes-admin@kubernetes kubernetes kubernetes-admin * sample-sa-context kubernetes sample-serviceaccount新たに作成したサービスアカウントでPodの情報が取得できるか試してみます。
pi@raspi001:~/tmp $ k get po Error from server (Forbidden): pods is forbidden: User "system:serviceaccount:default:sample-serviceaccount" cannot list resource "pods" in API group "" in the namespace "default"Errorになりました。sample-serviceaccountは何もRoleをバインドしていないからですね。
では、RoleBindingしていきます。元に戻ります。
pi@raspi001:~/tmp $ k config use-context kubernetes-admin@kubernetessample-role.yamlapiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1 kind: Role metadata: name: sample-role rules: - apiGroups: [""] resources: ["pods"] verbs: ["get", "watch", "list"]sample-rolebinding.yamlapiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1 kind: RoleBinding metadata: name: sample-rolebinding namespace: default roleRef: apiGroup: rbac.authorization.k8s.io kind: Role name: sample-role subjects: - kind: ServiceAccount name: sample-serviceaccount namespace: defaultpi@raspi001:~/tmp $ k apply -f sample-role.yaml pi@raspi001:~/tmp $ k apply -f sample-rolebinding.yamlでは、もう一度試してみます。
pi@raspi001:~/tmp $ k config use-context sample-sa-context pi@raspi001:~/tmp $ k get po NAME READY STATUS RESTARTS AGE ...おお、取得できました!
もとに戻しておきます。pi@raspi001:~/tmp $ k config use-context kubernetes-admin@kubernetesSecurityContext
コンテナに対してセキュリティ設定をすることができます。
例えば、Capabilitiesの追加・削除、実行するユーザ、グループの変更、ファイルのReadOnly化などができるそうです。sample-capabilities.yamlapiVersion: v1 kind: Pod metadata: name: sample-capabilities spec: containers: - name: nginx-container image: nginx:1.12 securityContext: capabilities: add: ["SYS_ADMIN"] drop: ["AUDIT_WRITE"]applyし、中身を確認してみます。
pi@raspi001:~/tmp $ k apply -f sample-capabilities.yaml pi@raspi001:~/tmp $ k exec -it sample-capabilities /bin/bash root@sample-capabilities:/# apt update && apt install libcap2-bin root@sample-capabilities:/# capsh --print | grep Current Current: = cap_chown,cap_dac_override,cap_fowner,cap_fsetid,cap_kill,cap_setgid,cap_setuid,cap_setpcap,cap_net_bind_service,cap_net_raw,cap_sys_chroot,cap_sys_admin,cap_mknod,cap_setfcap+eip root@sample-capabilities:/# exitcap_sys_adminが増えてますね。audit_writeは見つかりません。
そもそも、どんな種類があるのか分からなかったので、こちらを参考にしました。PodSecurityContext
Pod(全てのコンテナ)に対してセキュリティ設定をすることができます。
例えば、実行するユーザやグループの制御、root実行を拒否したり、カーネルパラメータを上書きすることもできます。sample-runuser.yamlapiVersion: v1 kind: Pod metadata: name: sample-runuser spec: securityContext: runAsUser: 99 # runAsGroup: 99 supplementalGroups: - 1001 - 1002 containers: - name: centos-container image: centos:7 command: ["/bin/sleep", "3600"]では、applyしています。
pi@raspi001:~/tmp $ k apply -f sample-runuser.yaml pi@raspi001:~/tmp $ k exec -it sample-runuser -- id uid=99(nobody) gid=99(nobody) groups=99(nobody),1001,1002 pi@raspi001:~/tmp $ k exec -it sample-runuser -- ps aux | grep sleep nobody 1 0.0 0.0 2032 372 ? Ss 14:02 0:00 /bin/sleep 3600実行したユーザがnobody(99)に変更されていますね。また、supplementalGroupsで、プライマリGIDに指定のGIDを追加することができます。
そのほか
PodSecurityPolicyや、NetworkPolicy、そして認証、認可のAdmissionControlというものもあるそうです。
お片付け
pi@raspi001:~/tmp $ k delete -f sample-serviceaccount.yaml -f sample-role.yaml -f sample-rolebinding.yaml -f sample-capabilities.yaml -f sample-runuser.yaml pi@raspi001:~/tmp $ k config delete-context sample-sa-context最後に
主にRBACについて学習しました。
複数人で開発する際は、コンテキストを分けて開発を進めるのが良いみたいですね。
今回で取り組んだように、誰がどの権限を持っているかをRBACで管理できるので、
必要以上の権限を与えられて事故るようなことは少なくなりますね。
(といっても、まだ個人でしか使ってないので分かりませんが...)
- 投稿日:2019-06-07T21:32:32+09:00
dockerのコンテナとイメージを削除する
未来電子テクノロジー株式会社でインターンをしている大学一回生です。
プログラミングの実務をしている先輩から、不要なdockerのコンテナとイメージを削除すると容量をかなり空けることができるとの情報をいただいたので、実行してみました。基本操作
コンテナの削除
動いているコンテナの確認
$ docker ps停止しているコンテナの確認
$ docker ps -aコンテナの削除
$ docker rm コンテナIDイメージの削除
存在するイメージの確認
$ docker imagesイメージの削除
$ docker rmi イメージIDイメージの削除でエラーが出た時の対処法
1.コンテナー>イメージの順に削除しているか確認
2.以下のコマンドで強制的に削除する
$ docker rmi -f イメージIDまとめ
プログラミング初心者なのでこんな簡単な操作にも詰まってしまいました。
けど、これでdockerを整理することができました。
なにか誤りがあればご指摘ください。
- 投稿日:2019-06-07T19:44:52+09:00
Visual Studioの謎のDockerfile
FROM mcr.microsoft.com/dotnet/core/runtime:2.2-stretch-slim AS base WORKDIR /app FROM mcr.microsoft.com/dotnet/core/sdk:2.2-stretch AS build WORKDIR /src COPY ["hoge-server/hoge-server.csproj", "hoge-server/"] RUN dotnet restore "hoge-server/hoge-server.csproj" COPY . . WORKDIR "/src/hoge-server" RUN dotnet build "hoge-server.csproj" -c Release -o /app FROM build AS publish RUN dotnet publish "hoge-server.csproj" -c Release -o /app FROM base AS final WORKDIR /app COPY --from=publish /app . ENTRYPOINT ["dotnet", "hoge-server.dll"]こんなファイルなんですけど、これを普通にたたくとバグるんですよね。
Step 7/17 : COPY ["hoge-server/hoge-server.csproj", "hoge-server/"] ERROR: Service 'hoge-server' failed to build: COPY failed: stat /var/lib/docker/tmp/docker-builder655807069/hoge-server/hoge-server.csproj: no such file or directoryあたりまえだけどファイルの指定位置がおかしい。Dockerfileがhoge-serverディレクトリの中にあるのに、hoge-serverディレクトリの中を見に行くみたいなことになってるんですよね。一旦上のディレクトリにDockerfileを持ち上げてるような動きをしてる。で、ためしにもちあげて実行すると普通にうごくんですよね。
なので同じDockerfileを二つ置いて運用しています。いやーなんでこんな仕様になってるのか教えてくれ~
- 投稿日:2019-06-07T17:18:51+09:00
Liberty on Docker(ubuntu)
websphere-libertyを日本語化してみた。
Dockerfileを以下としました。FROM websphere-liberty:19.0.0.5-kernel as builder ENV DEBCONF_NOWARNINGS yes FROM websphere-liberty:19.0.0.5-kernel USER root RUN apt-get update \ && apt-get -y install language-pack-ja \ && update-locale LANG=ja_JP.UTF-8 ENV LANG ja_JP.UTF-8 USER 1001 RUN /opt/ibm/wlp/bin/installUtility install --acceptLicense defaultServer \ && /opt/ibm/wlp/bin/securityUtility createSSLCertificate --server=defaultServer --password=test1234 EXPOSE 9080 9443 CMD ["/opt/ibm/wlp/bin/server", "run", "defaultServer"]最初、apt-getする際、rootにしなかったのでエラーになった。websphere-libertyはユーザdefault(idは1001)で動くよう作られているんですね。また、createSSLCertificateを実行するとき、パスワードが短かったので怒られました。。
サイズの差は以下の通りです。REPOSITORY TAG IMAGE ID CREATED SIZE websphere-liberty 19.0.0.5-kernelJP ff1fd694c225 About a minute ago 410MB websphere-liberty 19.0.0.5-kernel 30e139ebfe3e 9 days ago 344MB websphere-liberty 19.0.0.5-microProfile2 8acc64c44c06 6 days ago 459MB動かすとこんな感じです。
IBM J9 VM バージョン 8.0.5.36 - pxa6480sr5fp36-20190510_01(SR5 FP36) (ja_JP) で、defaultServer (WebSphere Application Server 19.0.0.5/wlp-1.0.28.cl190520190522-2227) を起動しています [AUDIT ] CWWKE0001I: サーバー defaultServer が起動されました。 [AUDIT ] CWWKE0100I: この製品は、開発使用向け、および限定的な実動使用向けにライセンスが交付されています。 全ライセン ス条項は以下で表示可能です: https://public.dhe.ibm.com/ibmdl/export/pub/software/websphere/wasdev/license/base_ilan/ilan/19.0.0.5/lafiles/ja.html [AUDIT ] CWWKG0093A: 構成ドロップイン・リソースを処理中です: /opt/ibm/wlp/usr/servers/defaultServer/configDropins/defaults/keystore.xml [警告 ] CWWKF0009W: サーバーは、いずれのフィーチャーもインストールするようには構成されていません。 [AUDIT ] CWWKF0011I: defaultServer サーバーは、Smarter Planet に対応する準備ができました。defaultServer サーバーは 0.546 秒で始動しました。別画面でexecし、dateコマンドを叩いた。
C:\Windows\System32>docker exec -it pensive_germain bash default@63e96552ede9:/$ ls bin config etc lib lib64 licenses media opt proc run srv tmp var boot dev home lib.index.cache liberty logs mnt output root sbin sys usr default@63e96552ede9:/$ date 2019年 6月 7日 金曜日 08:31:06 UTC default@63e96552ede9:/$UTCのままですね。JSTに変えてみます
C:\kazu>docker run -it -u 0 --rm websphere-liberty:19.0.0.5-kernelJP bash root@6be8a5c31c11:/# date 2019年 6月 7日 金曜日 08:57:37 UTC root@6be8a5c31c11:/# apt-get install tzdata パッケージリストを読み込んでいます... 完了 依存関係ツリーを作成しています 状態情報を読み取っています... 完了 以下のパッケージが新たにインストールされます: tzdata アップグレード: 0 個、新規インストール: 1 個、削除: 0 個、保留: 15 個。 167 kB のアーカイブを取得する必要があります。 この操作後に追加で 2,867 kB のディスク容量が消費されます。 取得:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 tzdata all 2019a-0ubuntu0.16.04 [167 kB] 167 kB を 1秒 で取得しました (103 kB/s) debconf: delaying package configuration, since apt-utils is not installed 以前に未選択のパッケージ tzdata を選択しています。 (データベースを読み込んでいます ... 現在 5888 個のファイルとディレクトリがインストールされています。) .../tzdata_2019a-0ubuntu0.16.04_all.deb を展開する準備をしています ... tzdata (2019a-0ubuntu0.16.04) を展開しています... tzdata (2019a-0ubuntu0.16.04) を設定しています ... debconf: unable to initialize frontend: Dialog debconf: (No usable dialog-like program is installed, so the dialog based frontend cannot be used. at /usr/share/perl5/Debconf/FrontEnd/Dialog.pm line 76.) debconf: falling back to frontend: Readline debconf: unable to initialize frontend: Readline debconf: (Can't locate Term/ReadLine.pm in @INC (you may need to install the Term::ReadLine module) (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.22.1 /usr/local/share/perl/5.22.1 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.22 /usr/share/perl5 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.22 /usr/share/perl/5.22 /usr/local/lib/site_perl /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl-base .) at /usr/share/perl5/Debconf/FrontEnd/Readline.pm line 7.) debconf: falling back to frontend: Teletype Current default time zone: 'Etc/UTC' Local time is now: Fri Jun 7 08:57:56 UTC 2019. Universal Time is now: Fri Jun 7 08:57:56 UTC 2019. Run 'dpkg-reconfigure tzdata' if you wish to change it. root@6be8a5c31c11:/# ln -sf /usr/share/zoneinfo/Asia/Tokyo /etc/localtime root@6be8a5c31c11:/# date 2019年 6月 7日 金曜日 17:58:12 JST root@6be8a5c31c11:/#これらを踏まえて、Dockerfileを変更しました。
FROM websphere-liberty:19.0.0.5-kernel as builder ENV DEBCONF_NOWARNINGS yes FROM websphere-liberty:19.0.0.5-kernel USER root RUN apt-get update \ && apt-get -y install language-pack-ja tzdata \ && update-locale LANG=ja_JP.UTF-8 \ && ln -sf /usr/share/zoneinfo/Asia/Tokyo /etc/localtime ENV LANG ja_JP.UTF-8 USER 1001 RUN /opt/ibm/wlp/bin/installUtility install --acceptLicense defaultServer \ && /opt/ibm/wlp/bin/securityUtility createSSLCertificate --server=defaultServer --password=test1234 EXPOSE 9080 9443 CMD ["/opt/ibm/wlp/bin/server", "run", "defaultServer"]Dockerfileを変更し、再度ビルド後、動かします。
C:\kazu>docker run -it --rm websphere-liberty:19.0.0.5-kernelJP bash default@c3b72744f090:/$ date 2019年 6月 7日 金曜日 23:28:32 JST default@c3b72744f090:/$ちゃんど、JSTになっています。
ベースをkernelにしたので、インストールされるfeatureはありません。server.xmlを修正して、インストールしようかな。
- 投稿日:2019-06-07T17:05:46+09:00
Docker環境ゴミ掃除3選
Docker使ってると気づいたらディスクがいっぱいになってたことありませんか?
私はあります。
そのたびに要らなくなったイメージを探して、消して、使ってないボリューム探して、消して、とかやってたのですが、つらくなってきたのでゴミ掃除的なコマンドを使うようになりました(docker system pruneとかね)。でも、実はこのコマンドだけじゃ全てのゴミを掃除できません。
Docker環境には他にも色んなゴミが眠ってて、ある程度ヘビーに使おうとすると他の方法も組み合わせて使う必要があります。
ただし、消してはいけないデータも意図せず消してしまう危険もあるので、状況に応じて適切な方法でゴミ掃除しましょう。本記事の読者として、以下のような方を想定しています。
- Dockerを使ったことがある
- イメージやコンテナなどの用語をとりあえず知っている
Dockerの資材
Dockerコンテナ周りの主な資材は以下があり、それぞれ使わなくなるとゴミができます。
資材 ゴミの例 イメージ もう使わなくなったコンテナのイメージや古いイメージなど。 コンテナ もう使わなくなって停止したコンテナなど。 ボリューム コンテナが停止/削除されてアンマウントされたボリュームなど。 ネットワーク もう使わなくなったネットワークなど。 図にすると以下のような感じです。
大事な点として、アプリエラーで停止しちゃったけど調査のために残しておきたいコンテナとか、
アンマウントしたけど運用データが入っているため残しておきたいボリュームなど、
運用によってゴミではないものもあります。そのため、どのゴミ掃除コマンドでどこまで掃除されるか、をきちんと理解して使用する必要があります。
ゴミ掃除コマンド
dockerのコマンドでpruneオプションが使えるものがいくつかあり、それらをゴミ掃除コマンドと呼んでいます。
いろいろありますが、基本的には以下があれば私は大丈夫だと思います。
- 【コマンド1】 docker system prune [-f]
- 【コマンド2】 docker image prune -a [-f]
- 【コマンド3】 docker volume prune [-f]
シチュエーション
以下に、シチュエーションごとに使うとよいゴミ掃除コマンドを紹介します。
ただし、停止状態のコンテナも消えるため、コンテナでエラーが発生して停止したコンテナを調査する場合などは実行してはいけません。a. コンテナ置き換えのあと
とりあえず以下のコマンドを順番に打っとけば大丈夫です。
-fを付けると確認なしで実行されます。
- 【コマンド1】 docker system prune [-f]
- 【コマンド2】 docker image prune -a [-f]
これを実行すると以下が削除されます。
- すべての未使用コンテナ(停止状態など)
- すべての未使用ネットワーク(どのコンテナにも接続されていないものなど)
- どのコンテナのベースにもなっていないすべてのイメージ
(docker system pruneの
Extended descriptionや docker image pruneのExtended descriptionを参照)ボリュームは削除されないので運用データが消える心配はありません。
使っていないコンテナとかネットワークは、使う時にまた作ればいいので大丈夫。アプリのバージョンアップなどでイメージが更新されたら、
新イメージでコンテナを作り直します。
すると、旧イメージが残るため、docker image pruneで消しています。b. サービスを停止してDocker上の全ての資材を削除するとき
[a. コンテナ置き換えのあと]のコマンドの後に、
docker volume pruneも実行するとよいです。
- 【コマンド1】 docker system prune [-f]
- 【コマンド2】 docker image prune -a [-f]
- 【コマンド3】 docker volume prune [-f]
これを実行すると以下が削除されます。
- すべての未使用コンテナ(停止状態など)
- すべての未使用ネットワーク(どのコンテナにも接続されていないものなど)
- どのコンテナのベースにもなっていないすべてのイメージ
- マウントされていないすべてのボリューム
(docker volume pruneの
Extended descriptionを参照)サービス停止時は、ボリュームに入った運用データも不要になります(どこかにバックアップはするかもしれませんが)。
したがって、コンテナ停止削除後、docker volume pruneでボリュームも削除しています。以上!
- 投稿日:2019-06-07T16:29:23+09:00
REDASH7でクエリが実行出来ない問題の解消
REDASH6からREDASH7へ移行しました。
無事にアップデート出来たと思ったのですが、クエリー作成画面で「Execute」をクリックしたのですが
何も結果が表示されない問題が発生しました。
解消方法までの手順を纏めました。Dockerのログを確認
Dockerのログを確認します。
コンテナのログは以下のコマンドで表示出来ます。# docker ps CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES 9e306be1ae43 redash/nginx:latest "nginx -g 'daemon of…" 6 hours ago Up 6 hours 0.0.0.0:80->80/tcp, 443/tcp redash_nginx_1 56ede752534b redash/redash:7.0.0.b18042 "/app/bin/docker-ent…" 6 hours ago Up 6 hours 0.0.0.0:5000->5000/tcp redash_server_1 613adc931afc redis:3.0-alpine "docker-entrypoint.s…" 6 hours ago Up 6 hours 6379/tcp redash_redis_1 198297742e8c redash/redash:7.0.0.b18042 "/app/bin/docker-ent…" 6 hours ago Up 6 hours 5000/tcp redash_worker_1 207215d21524 postgres:9.5.6-alpine "docker-entrypoint.s…" 6 hours ago Up 6 hours 5432/tcp redash_postgres_1workerコンテナで実行されているはずなのでworkerコンテナのログを確認します。
# docker logs redash_worker_1「Execute」でSQL実行時に「InvalidToken」の文字列が出力されている事を発見。
どうやらdocker-compose.ymlのworker設定に「REDASH_COOKIE_SECRET」が入っていない事が原因の模様。
workerの設定に以下を追加し、コンテナ再起動。docker-compose.ymlREDASH_COOKIE_SECRET: veryverysecret# docker-compose -f docker-compose.yml down# docker-compose -f docker-compose.yml up -dこれで無事解消されました。
- 投稿日:2019-06-07T16:01:15+09:00
全文検索サーバを構築した話 その2(docker構築詳細編)
その1ではざっくりと全文検索サーバ構築の経緯と構築環境について記載しました。
その2ではもう少し掘り下げて環境構築のメモを記載します。(ほぼWebエビデンス)OS環境
OSバージョン
$ cat /etc/redhat-release CentOS Linux release 7.6.1810 (Core)カーネルバージョン
$ uname -a Linux [ホスト名] 3.10.0-957.12.2.el7.x86_64 #1 SMP Tue May 14 21:24:32 UTC 2019 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linuxdockerインストール
dockerはCentOS標準のdockerをyumでインストールしました。
$ sudo yum -y install docker インストール: docker.x86_64 2:1.13.1-96.gitb2f74b2.el7.centos 依存性関連をインストールしました: PyYAML.x86_64 0:3.10-11.el7 atomic-registries.x86_64 1:1.22.1-26.gitb507039.el7.centos audit-libs-python.x86_64 0:2.8.4-4.el7 checkpolicy.x86_64 0:2.5-8.el7 container-selinux.noarch 2:2.95-2.el7_6 container-storage-setup.noarch 0:0.11.0-2.git5eaf76c.el7 containers-common.x86_64 1:0.1.35-2.git404c5bd.el7.centos device-mapper-event.x86_64 7:1.02.149-10.el7_6.7 device-mapper-event-libs.x86_64 7:1.02.149-10.el7_6.7 device-mapper-persistent-data.x86_64 0:0.7.3-3.el7 docker-client.x86_64 2:1.13.1-96.gitb2f74b2.el7.centos docker-common.x86_64 2:1.13.1-96.gitb2f74b2.el7.centos libaio.x86_64 0:0.3.109-13.el7 libcgroup.x86_64 0:0.41-20.el7 libsemanage-python.x86_64 0:2.5-14.el7 libyaml.x86_64 0:0.1.4-11.el7_0 lvm2.x86_64 7:2.02.180-10.el7_6.7 lvm2-libs.x86_64 7:2.02.180-10.el7_6.7 oci-register-machine.x86_64 1:0-6.git2b44233.el7 oci-systemd-hook.x86_64 1:0.1.18-3.git8787307.el7_6 oci-umount.x86_64 2:2.3.4-2.git87f9237.el7 policycoreutils-python.x86_64 0:2.5-29.el7_6.1 python-IPy.noarch 0:0.75-6.el7 python-backports.x86_64 0:1.0-8.el7 python-backports-ssl_match_hostname.noarch 0:3.5.0.1-1.el7 python-ipaddress.noarch 0:1.0.16-2.el7 python-pytoml.noarch 0:0.1.14-1.git7dea353.el7 python-setuptools.noarch 0:0.9.8-7.el7 setools-libs.x86_64 0:3.3.8-4.el7 subscription-manager-rhsm-certificates.x86_64 0:1.21.10-3.el7.centos yajl.x86_64 0:2.0.4-4.el7 完了しました!dockerサービス自動起動設定
$ sudo systemctl enable docker Created symlink from /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/docker.service to /usr/lib/systemd/system/docker.service.dockerサービス起動と確認
$ sudo systemctl start docker $ sudo systemctl status docker ● docker.service - Docker Application Container Engine Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/docker.service; enabled; vendor preset: disabled) Active: active (running) since 金 2019-06-07 14:42:00 JST; 23s ago Docs: http://docs.docker.com Main PID: 20950 (dockerd-current) CGroup: /system.slice/docker.service tq20950 /usr/bin/dockerd-current --add-runtime docker-runc=/usr/libexec/docker/docker-runc-current --defau... mq20958 /usr/bin/docker-containerd-current -l unix:///var/run/docker/libcontainerd/docker-containerd.sock ...Fessのイメージを取得する
$ sudo docker pull codelibs/fess:latest Trying to pull repository docker.io/codelibs/fess ... latest: Pulling from docker.io/codelibs/fess e79bb959ec00: Pull complete d4b7902036fe: Pull complete 1b2a72d4e030: Pull complete de423484a946: Pull complete 9ce08128c662: Pull complete 53b0cf80b370: Pull complete 52bd533f444d: Pull complete f39d9fa4825b: Pull complete ffbf2fa304a8: Pull complete 560b4917ad19: Pull complete b19453126120: Pull complete 3e02eca524a0: Pull complete 5145f1f6b740: Pull complete 9c0519ef74ee: Pull complete Digest: sha256:f8c9818af2035b2b5489756c609bf973f8cc02c460874f4f9e5e8672f7c105c9 Status: Downloaded newer image for docker.io/codelibs/fess:latestFessのdockerコンテナを作成する
dockerのコンテナ名は、"全文検索"を英訳すると"Full text search"となるため、頭文字を取って"fts"にしました。
また、メインサービスがfessになるため、ポート指定してつながなくても良いようにホストの80番ポートをコンテナ内の
fessの8080ポートにマッピングしています。$ sudo docker run -d -p 80:8080 --name fts codelibs/fess:latest c266e8c6c14d2514a60d987d1beb4c6c5a187b2ba5142a6087a464fc3261b17bコンテナのタイムゾーンを変更する
コンテナ内のOS環境の標準タイムゾーンがUTCのため、日本時間のJSTに変更します。
$ sudo docker exec -it fts rm /etc/localtime $ sudo docker exec -it fts ln -s /usr/share/zoneinfo/Asia/Tokyo /etc/localtime # 時間確認 $ sudo docker exec -it fts date Fri Jun 7 15:01:10 JST 2019 $ sudo docker exec -it fts ls -l /etc/localtime lrwxrwxrwx 1 root root 30 Jun 7 15:00 /etc/localtime -> /usr/share/zoneinfo/Asia/TokyoFess動作確認
curlで80番ポートにHTTPしてヘッダが読めるか確認します。
$ curl --head http://localhost HTTP/1.1 200 Set-Cookie: JSESSIONID=4937956A71BB0E6DE7D7B974BB39D7F0; Path=/; HttpOnly Pragma: no-cache Cache-Control: no-cache, no-store Expires: Thu, 01 Dec 1994 16:00:00 GMT Content-Type: text/html;charset=UTF-8 Transfer-Encoding: chunked Date: Fri, 07 Jun 2019 06:08:41 GMTブラウザ動作確認
まとめ
こんな感じで非常に簡単にFessによる全文検索サーバの環境が構築できます。
実際やっていただければわかりますが、イメージのダウンロード時間を除けばものの数分でFessが
利用できる環境を構築することができます。おまけ
割愛しておりますが、selinuxを無効、firewalldの停止をしております。
selinuxとfirewalldを有効にして利用する場合はもうひと手間手順が必要かもしれません…
その辺は別の詳しい方に聞いてください…(弱気)次回こそ、PDF変換手順の説明を書きます!
- 投稿日:2019-06-07T15:49:01+09:00
Docker初心者が学ぶならこの順番が分かりやすかった
はじめに
この記事の内容は以下の方向けです。
・Dockerって何?って人
・学び始めたけどいまいちピンってこない人あくまでも学習の取っ掛かりに過ぎないと思ってください。
それ以外の人にはあまり有益な情報は無いと思いますので、
回れ右をして私より有能なエンジニアの記事を探してください。結論
コンテナ、Docker Compose、Docker Fileの順で学ぶのが分かりやすい!!
なぜそうなったのか
資料は探してみたけどDockerの成り立ちとか概念とかばっかり...
そういうものは最終的に書き方のリファレンスなって理解が進まない...
自分はそんなのが知りたいわけじゃない...
といった私の経験から出た結論がというわけで重要点です。
・コンテナ
・Docker Compose
・Docker File私は上記の3点がDockerを理解するうえで最低限なポイントと感じました。
そしてこの順序で学習していくと今までこんがらがっていたところがするすると紐解けました。
以下は上記の重要点をまとめたものとなります。
学習の参考資料としてお使いください。コンテナ
OSSであるDocker上で動く環境一つの単位です。
基本はOS、ミドルウェア、アプリケーションで構成された環境のことを指します。そして、このコンテナをDocker Engine上に複数配置して環境を構築します。
Docker Compose
Dockerの初期学習をした方の中にはこういった経験をした人はありませんでしたか?
これは非常にめんどくさい!!
できればボタン一つ、コマンド一つで環境の立ち上げや終了をしてほしいと思うのがエンジニアの心情だと思います。Docker Composeはymlファイルという定義ファイルを記述しコマンドを実行すると定義ファイルに書かれた内容(複数のコンテナの作成や作成時の環境変数など)を人の代わりにやってくれる優れものなのです。
Docker File
Docker FileとはDockerイメージを作るため情報を記載したファイルです。
※Dockerイメージとはコンテナを作る際のレシピみたいなものです。
コンテナはDockerイメージを元に作成されます。既存のDocker Imageにカスタマイズを施すために使用することが主たる使用方法です。
例えば、公開されているLinux系OSのDocker Imageをベースにほかのパッケージやアプリを入れたオリジナルの環境を作る時などに使用します。まとめ
今までの開発環境のセッティングが石器時代に感じるぐらい
簡単に環境がセッティングできる素晴らしさ知ったらもう手放せませんね。
- 投稿日:2019-06-07T09:52:52+09:00
ojichatをSlackに流す
最近ojichatが流行ってますね。
普段会社の勤怠はSlackに投稿してるんですが、あまりに自分の遅刻が多く自分のメッセージで埋まるので、ojichatを流すことにしました。https://github.com/naomichi-y/ojichat-slack-bot
和む。
- 投稿日:2019-06-07T06:37:44+09:00
gcc on Docker
gccの最新版をビルドしてみます。
alpine gccのDockerfileを使用します。FROM alpine as alpine ARG GCC_VERSION ENV GCC_VERSION=${GCC_VERSION} FROM alpine as builder RUN apk add --quiet --no-cache \ build-base \ binutils \ dejagnu \ isl-dev \ make \ mpc1-dev \ mpfr-dev \ texinfo \ zlib-dev RUN wget -q https://ftp.gnu.org/gnu/gcc/gcc-${GCC_VERSION}/gcc-${GCC_VERSION}.tar.gz && \ tar -xzf gcc-${GCC_VERSION}.tar.gz && \ rm -f gcc-${GCC_VERSION}.tar.gz WORKDIR /gcc-${GCC_VERSION} RUN ./configure \ --prefix=/usr/local \ --build=$(uname -m)-alpine-linux-musl \ --host=$(uname -m)-alpine-linux-musl \ --target=$(uname -m)-alpine-linux-musl \ --with-pkgversion="Alpine ${GCC_VERSION}" \ --enable-checking=release \ --disable-fixed-point \ --disable-libmpx \ --disable-libmudflap \ --disable-libsanitizer \ --disable-libssp \ --disable-libstdcxx-pch \ --disable-multilib \ --disable-nls \ --disable-symvers \ --disable-werror \ --enable-__cxa_atexit \ --enable-default-pie \ --enable-languages=c,c++ \ --enable-shared \ --enable-threads \ --enable-tls \ --with-linker-hash-style=gnu \ --with-system-zlib RUN make --silent -j $(nproc) && \ make --silent -j $(nproc) install-strip && \ gcc -v FROM alpine RUN apk add --quiet --no-cache \ autoconf \ automake \ binutils \ cmake \ file \ git \ gmp \ isl \ libc-dev \ libtool \ make \ mpc1 \ mpfr3 \ musl-dev \ pkgconf \ zlib-dev COPY --from=builder /usr/local/ /usr/ RUN ln -s /usr/bin/gcc /usr/bin/cc WORKDIR /srcビルドは以下で行います。
docker build --build-arg GCC_VERSION=9.1.0 -t kazu_gcc:9.1.0 .今、あるイメージは以下となります。
C:\Windows\System32>docker images REPOSITORY TAG IMAGE ID CREATED SIZE kazu_gcc 9.1.0 549b309e4863 7 hours ago 251MB websphere-liberty 19.0.0.5-javaee8 517f9afc2361 5 days ago 502MB websphere-liberty 19.0.0.5-kernel 30e139ebfe3e 9 days ago 344MB kazu_gcc 10.0.0 6aa1e6ab2515 2 weeks ago 1.73GB ubuntu 19.10 3f269de19be1 3 weeks ago 76.1MB alpine 3.9.4 055936d39205 3 weeks ago 5.53MB alpine latest 055936d39205 3 weeks ago 5.53MB busybox 1.30.1 64f5d945efcc 4 weeks ago 1.2MB busybox latest 64f5d945efcc 4 weeks ago 1.2MB debian stretch-slim 92d2f0789514 4 weeks ago 55.3MB n0madic/alpine-gcc 9.1.0 db86eea6352b 4 weeks ago 251MBせっかくなので、実行環境を作って動かしてみた。
hello.c#include <stdio.h> void main(void) { printf("Hello, world!\n"); }実行環境構築用のDockerfileを用意する。
FROM kazu_gcc:9.1.0 as builder COPY hello.c /src RUN gcc /src/hello.c -o hello FROM scratch ADD busybox-1.30.1.tar.gz / COPY --from=builder /src/hello /bin/ CMD ["/bin/hello"]ビルドは以下となります。
C:\kazu>docker build -f DockerfileExec -t kazu_gcc:exec . Sending build context to Docker daemon 1.428MB Step 1/7 : FROM kazu_gcc:9.1.0 as builder ---> 549b309e4863 Step 2/7 : COPY hello.c /src ---> d6e9031c5ce2 Step 3/7 : RUN gcc /src/hello.c -o hello ---> Running in 336708e08b1b Removing intermediate container 336708e08b1b ---> 38e88000f53e Step 4/7 : FROM scratch ---> Step 5/7 : ADD busybox-1.30.1.tar.gz / ---> b4f683bb4898 Step 6/7 : COPY --from=builder /src/hello /bin/ ---> 5d35e1204bbf Step 7/7 : CMD ["/bin/hello"] ---> Running in 8ad465f15370 Removing intermediate container 8ad465f15370 ---> 8e34b180254c Successfully built 8e34b180254c Successfully tagged kazu_gcc:exec SECURITY WARNING: You are building a Docker image from Windows against a non-Windows Docker host. All files and directories added to build context will have '-rwxr-xr-x' permissions. It is recommended to double check and reset permissions for sensitive files and directories. C:\kazu>後は出来上がったイメージを動かします。
C:\kazu>docker run -it --rm kazu_gcc:exec Hello, world! C:\kazu>当然、実行用のイメージサイズは小さいです。
REPOSITORY TAG IMAGE ID CREATED SIZE kazu_gcc exec 8e34b180254c 30 minutes ago 1.44MB